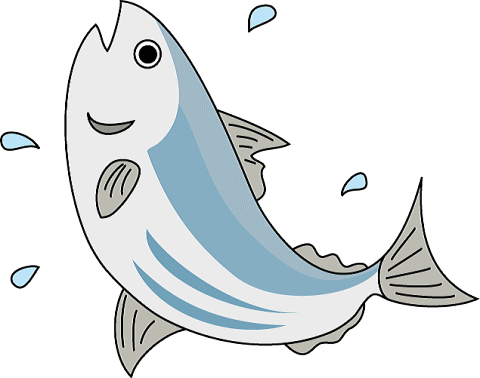 『目に青葉 山ほととぎす 初ガツオ』
『目に青葉 山ほととぎす 初ガツオ』
今日は台風シーズンに突入した今とは少しズレたお話です。そして戦国時代というよりも、江戸時代のお話。謡にもうたわれている様に、初夏の訪れをしらせる【初ガツオ】は、江戸時代にも人気でした。しかし人気の高い旬のものは、値段も高いうのが当時の常識。カツオも高かったんですね。
そこで江戸時代(といっても数百年間ありますが)いったい【初ガツオ】はいくらだったのか調べてみました。
まず江戸時代後期の十八世紀に、初ガツオ一尾の値段が【二両三分】という記録が残っています。そして【二両三分】は、いったいどのくらいなのか?【両・分】を現代の【円】に換算する方法はいくつかありますが、日本史の舞台裏【歴史の謎研究会】という資料にその結果が載っています。それによると、当時の【二両三分】は現代では約16万との事。かなりの値段ですよね。
もちろん庶民が気軽に口に出来るものではなかったのですが、しかしなんとかして食べてみたいもの。入手方法も知恵を絞っていたんですね。そこでこんな川柳もできました。
『女房を 質に入れても 初ガツオ』
なんかシャレにならない川柳です。あとカツオは(走りが早い)、つまり鮮度が落ちるのが早い魚で、こういったものは、すぐに値崩れし、庶民でも買うことができました。しかし、『はずかしや 医者にカツオの 値が知れる』という句も残っています。
なんとか安くなったカツオを食べたのはよかったのですが、傷んでおり腹痛になった人の句ですね。昔の初カツオは必死のイベントだったみたいです。